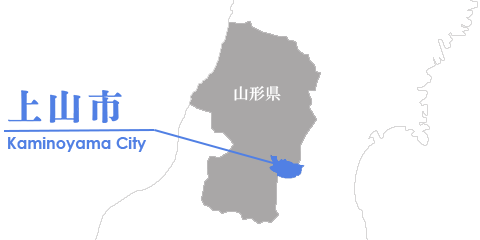【事業は終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付)の給付について
令和7年10月31日をもって、事業は終了しました。
制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」が行われました。また、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付(※)」として令和6年度に支給しました。調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(※)当初調整給付とは、令和6年度に実施した事業です。(令和6年10月31日に事業は終了しています。)/soshiki/8/chousei06.html
【不足額給付Ⅰ】
対象者
令和7年1月1日時点で上山市にお住いの方で、次の1または2のいずれかに該当する方であって、不足額給付時(基準日時点)の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付所要額を上回る方。
1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る方
2. 令和6年度個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
給付額
下記のとおり1万円単位で支給。
算出方法は、次のとおりです。
- 「所得税分控除不足額(1)」の算出方法
定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年分所得税額(減税前)=(1)(<0の場合は0) - 「住民税分控除不足額(2)」の算出方法
定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年度住民税所得割額(減税前)=(2)(<0の場合は0) - (1)+(2)(1万円単位に切り上げ)-令和6年度定額減税調整給付金=不足額給付金
- 所得税および住民税所得割額は、上山市で把握している令和7年8月8日時点の課税資料で算定します。
- 扶養親族は、所得税は令和6年12月31日時点、住民税は令和5年12月31日時点で判定します。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円の場合、調整給付所要額は「0」となり、不足額給付Ⅰの対象ではなくなります。
- 国税である所得税については、不足額給付時における令和6年分所得税額の算出においては、令和6年分の課税資料をもとに、独自のシステムを使用して算出しています。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定しますので、給付額への影響はほとんどないものと思われます。もし給付額に影響があると思われる場合は、そのことが分かる書類をご準備いただき、内線131~134 税務課住民税係までご連絡ください。
【不足額給付Ⅱ】
対象者
以下のア~ウすべてに該当する人。
ア.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)。
イ.税制度上、扶養親族の対象外である(注1)。
ウ.過去に実施した低所得世帯向け給付(注2)を受給した世帯の世帯主または世帯員ではない。
(注1)青色(白色)事業専従者、合計所得金額が48万円超で扶養親族になれない人など。
(注2)上山市または他自治体から下記の給付金を受給した世帯主・世帯員を指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付額
1人当たり原則4万円(定額)を支給。
令和6年1月1日に国外へ居住していた人は3万円を支給。
注意事項
以下の方は対象外となります。
- 2025年1月1日時点で非居住者
- 死亡している方
- 未申告の方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
詳しい詳細については、各ホームページをご覧ください。
定額減税について(国税庁ホームページ) https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>
定額減税補足給付金について(内閣府ホームページ)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク>
申請方法
支給のお知らせ (振込先口座を市で把握できている方)
令和7年8月27日(水曜日)以降、順次郵送しています。
当初調整給付の受給済口座または公金受取口座を記載していますので、原則申請の手続きは不要です。ただし、支給のおしらせが届いた方で、下記に該当する方のみお手続きをお取りください。
- 給付を辞退したい方
- 口座を解約した方
- 振込口座を変更したい方
令和7年9月12日(金曜日)まで(必着)、辞退届または変更届を申し出てください。
様式を自身でホームページより印刷し郵送するか、様式を郵送しますので下記担当までお電話で申し出てください。郵便事情により2~3日かかる場合がありますので、早めに提出してください。
支給確認書 (振込先口座を市で把握できていない方)
令和7年8月27日(水曜日)以降、順次郵送しています。
要件を確認後、必要事項を記入し、ご案内に記載した必要書類を同封のうえ、令和7年10月31日(金曜日)まで、
同封した返信用封筒で確認書を返送してください。窓口の混雑を避けるため、郵送による提出にご協力ください。当日消印有効。
申請が必要な方
令和7年10月31日(金曜日)まで申請してください。郵送の場合、当日消印有効。
- 「支給のお知らせ」、「支給確認書」が届かない方で、上記に該当すると思われる方は申請してください。なお、未申告の方には 「支給のお知らせ」・「確認書」は送付していません。確定申告書等を済ませ、給付金の対象に該当する方は、自ら申請をお願いします。
- 転入された方は、下記「上山市へ転入された方へ」をご覧ください。
- 上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(※)に該当するときは、対象となる場合があります。
(※)ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
上山市へ転入された方へ
令和6年度の住民税を他市区町村で課税されていた方が、上山市に転入し、令和7年1月1日時点に上山市にお住まいの方は、
不足額給付に該当となる場合、給付の実施自治体は「上山市」となります。
上山市は転入者の利便性の向上のため、以前お住いの自治体より転入者の所得と給付状況を把握し、対象と見込まれる方へ「確認書」を送付しています。
上山市より「確認書」が届いていない転入者のうち、給付の要件に当たると思われる方は、下記様式から申請書をダウンロードし提出されるか、「税務課 住民税係(内線134)」までご相談ください。
転入前自治体で未申告だった方で、その後確定申告等をした方は、上山市では把握できかねますので、給付金に該当すると思われる方は、下記申請様式より申し出てください。令和7年10月31日(金曜日)まで申請してください。郵送の場合、当日消印有効。
上山市から転出された方へ
(申請方法は令和7年1月1日時点でお住いの自治体によって異なります。給付時期も異なりますので、お住いの自治体のホームページや広報誌でお確かめください。)
令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)を上山市から受給し、その後令和7年1月1日時点で他市区町村にお住まいの方は、
不足額給付に該当となる場合、給付の実施自治体は「令和7年1月1日時点でお住いの自治体」となります。
国では申請型を想定していますが、自治体によって申請方法が異なるため、上山市から交付した支給決定通知書が必要になる場合があります。
支給決定通知書の紛失や、受給実績の証明が必要な方は、送料の切手代を貼った返信用封筒を同封し、下記様式または申請先自治体の様式(指定されている場合)を送付して請求してください。概ね1週間程度で返信しますが、提出先自治体の申請期限に間に合うように余裕をもって申請してください。
よくあるご質問
Q1 令和6年度に定額減税補足給付金(調整給付)をすでに受給しましたが、支給のお知らせが届きました。給付対象になったのはなぜですか。
A1 個々の状況により理由は異なりますが、下記のような場合が考えられます。
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・税の更生(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
・扶養する親族等が増えた場合
Q2 合計所得金額が48万円以上かどうかは、どうやって確認できますか。
A2 給与所得の源泉徴収票(令和6年分)、令和7年度所得証明書、令和7年度住民税の特別徴収税額通知書、令和7年度住民税の普通徴収税額通知書等で確認できます。
Q3 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。減税しきれない金額は給付対象になりますか。
A3 対象要件を満たしていれば、不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、この場合は住民税分(1万円×減税対象人数)は含まれず、所得税分(3万円×減税対象人数)のみが不足額給付の支給対象となります。
Q4 課税されていた家族が令和6年中に亡くなりました。その人への不足額給付はどうなりますか。
A4 不足額給付は、令和7年1月1日に上山市に住所があることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。
Q5 令和7年1月2日以降に家族が死亡しました。不足額給付の対象になると思われますが、給付金はもらえますか。
A5 不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の意思表示が必要になります。
令和7年1月2日以降、支給対象者が不足額給付確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。不足額給付確認書の返送・申請後亡くなられた場合は、相続人へ改めて振込先の照会を行います。
Q6 昨年、定額減税しきれないと見込まれ、定額減税補足給付金(調整給付)を受給しましたが、年末調整の結果、定額減税しきれることとなりました。昨年受給した給付金は返還の必要はありますか。
A6 結果的に過大に受給することとなっても、返還の必要はありません。
Q7 令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)を申請していなかったことに気づきました。令和7年度に受給できますか。
A7 期限までに申請のなかったものは辞退したものとみなすため、令和6年度の分を給付する事はできませんが、不足額給付の算定の際に
(令和6年度調整給付で申請すれば受給できた金額)<(令和7年度不足額給付算定で判明した不足額)であれば、差額のみ1万円単位で不足額給付として受給可能です。
給付金を装った詐欺にご注意ください
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。