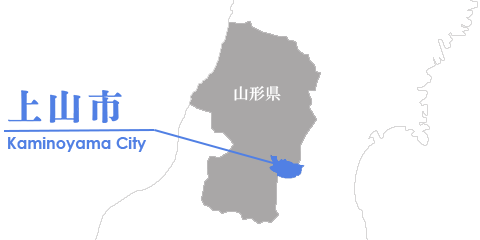【事業は終了しました】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)事業について
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について
制度の概要
なお、迅速な給付を行う観点から、減税額確定を待たずに令和6年に入手可能な課税情報をもとに前倒しで給付を行います。
そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額等確定後、給付額に不足のあること等が判明した場合には、追加で不足分の給付(不足額給付)を令和7年度に行うことが検討されています。(実施時期・方法等未定)
【注意事項】
・住民税が課税となる申告すべき所得があるのに、確定申告等を済ませていない未申告である人は対象外です。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
・推計で給付額を算出しているため、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績が判明した際に、過大に給付を行っていたことが判明する可能性がありますが、返還は求めません。
対象者
令和6年1月1日現在に上山市に住民登録があり、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が次の1または2のいずれかに該当する方。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額※2」を上回る
2.住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が「令和6年度住民税所得割額」を上回る
※1 納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(ただし、国外居住者は対象から除きます。)
※2 市民のみなさんにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年分の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。
給付額
次の1と2の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
- 所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
- 住民税所得割の定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額
算出例
(例)納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は6万4千円、令和6年度住民税額(減税前)3万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数2人)=9万円
住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数2人)=3万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:9万円-令和6年分推計所得税額(減税前):6万4千円=2万6千円
(2)個人住民税分控除不足額
住民税分定額減税可能額:3万円-令和6年度住民税額(減税前)3万5千円=5千円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額:2万6千円+(2)住民税分控除不足額:5千円=3万1千円
支給額は4万円(1万円単位で切り上げ)となります。
受給方法
【事業は終了しました】
対象となる方へ令和6年8月28日(水)に書類を発送しました。順次郵送されますので、お待ちください。
「支給のお知らせ」が届いた方
上山市で公金受取口座を把握できた方へ、「支給のお知らせ」を送付しています。
記載内容に変更がなければ、約1カ月程度で振り込みますので、返信は不要です。
お知らせの記載内容から変更がある方のみ、令和6年9月13日(金)まで下記①~④を同封して返信用封筒で郵送してください。
➀ 「支給のお知らせ」の用紙 (必須)
② 通帳又はキャッシュカードのコピー(変更がある方)
③ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)のコピー(必須)
(注)通帳等をコピーする際は、金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ氏名)が確認できる部分 (通帳の場合は、表紙をめくった見開き部分)のコピーをとり、添付台紙に貼って提出してください。
④ 各数値について重大な相違がある方のみ、確定申告書などのコピーを同封(該当する方)
「支給確認書」が届いた方
令和6年10月31日(木、消印有効) まで返信してください。
下記①~④を同封して返信用封筒で郵送してください。
➀ 「支給確認書」の用紙 ご覧いただき、必要事項を記入してください。(必須)
② 通帳又はキャッシュカードのコピー(必須)
③ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)のコピー(必須)
(注)通帳等をコピーする際は、金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ氏名)が確認できる部分 (通帳の場合は、表紙をめくった見開き部分)のコピーをとり、添付台紙に貼って提出してください。
④ 各数値について重大な相違があるのみ、確定申告書などのコピー(該当する方)
給付の辞退を希望する方(給付を受け取らないことを希望する方)
令和6年9月13日(金)まで、福祉課地域福祉係(023-672-1111内線147)へお電話ください。
Q&A
Q1.事業の詳細について詳しく教えてください。
A:事業の詳細についてはこちらをご覧ください。
定額減税について (所得税)<外部リンク> (住民税)
各給付について 内閣官房ホームページ<外部リンク>
Q2.「自ら申請しないと貰えない」と聞きました。自分が給付に該当するか知りたい。
A:内閣官房でフローチャート<外部リンク>がありますので参考にしてください。
なお、上山市は非課税世帯等への令和5年度の同給付(7万円・10万円)は既に終了していますのでご注意ください。
給付の方法は各市区町村で異なります。上山市は、課税状況を把握できており、給付の要件に該当すると見込まれる方へ、確認書を送付します。
<参考>
自分の所得や住民税の課税状況を確認する方法
課税証明書等(有料)、住民税の税額通知書(※)で確認できます。
※給与所得から特別徴収されている方は、概ね5月~6月頃に勤務先を通して送付しています。
※普通徴収で住民税が課税されている方は6月中旬以降、自宅へ郵送しています。
通知書の見方がわからない方は、課税されている自治体の住民税課税担当課へお問い合わせください。
Q3.令和6年1月2日以降に支給対象者が死亡した場合、給付はどうなりますか。
A:調整給付の場合
「確認書」の返送前に亡くなられた場合、調整給付は支給されませんが、確認書の返送後に亡くなられた場合は、相続の対象となりますので、下記まで必ずお問合せ下さい。
支給のお知らせ送付後に亡くなられた場合も、下記までお問い合わせください。
なお、発送の都合上、行き違いで亡くなられた方へ送付されている場合がありますが、ご了承ください。
Q4.修正申告等により、所得税や住民税額の変更がありました。調整給付はどうなりますか。
A:令和6年8月20日まで税務システムに反映されたものについては、調整給付に反映されています。それ以降の申告は反映されておりません。よって、8月21日以降税務システムに反映された方は、令和7年度に不足給付を予定していますので、その際に要件を満たすものについては、不足給付分として給付を行います。ただし、調整給付の対象者では無くなった場合、返還を求めることがありますので、ご相談ください。
Q5.令和6年1月1日は上山市に住民登録がありましたが、令和6年1月2日以降上山市から転出しました。給付はどの自治体から受け取れますか。
A:転出した方でも、基準日に上山市に住民登録があり、給付が見込まれる方には支給のお知らせ又は確認書を8月28日に送付します。ただし、転居を複数回行っている等で上山市が現住所が把握できないことも考えられますので、書類が送られてこない方はお問い合わせ下さい。
Q6.定額減税前の税額が、所得税なし(0円)、かつ住民税所得割額なし(0円)の場合は、調整給付はどのように取り扱うこととなりますか。
A:令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人住民税所得割がともに0円の場合、調整給付(当初)の対象にはなりません。ただし、令和7年度に予定している不足給付の際に、一定の要件を満たす場合は、給付の対象となります。
【9月6日追記】令和6年8月28日以降、福祉課に多く寄せられたお問い合わせ内容についてご案内します。
Q7.自分には書類が届いたが、家族には届かない人がいたのはなぜか。
A:あくまで、定額減税しきれないと見込まれる方のみが対象となりますので、非課税の方や、定額減税を全額受け切れると見込まれる方には発送していません。ただし、令和6年分の所得税が確定したのち、定額減税しきれない分があるとわかった際は、令和7年度に行う不足給付で対応します。
Q8.令和5年中の所得を用いて推計で給付額を算出されているが、令和5年中と比べて、令和6年分の所得に変動があることが既に分かっている。多く給付を受け取ることになるのではないか。返還は必要か。
A:令和6年分の所得税額および定額減税の実績が判明した際に、過大に給付を行っていたことが判明する可能性もありますが、返還は求めません。
Q9.勤務先で定額減税を受けているが、給付も受け取ってよいのか。
A:上記Q8と同様です。令和6年度の調整給付は、6年分の所得税額を推計し給付をしているため、現在の定額減税の実情は反映されていません。
結果的に、給付が過支給になっても返還は求めませんので、定額減税を勤務先で受けると同時に調整給付は受け取ってよいことになっています。