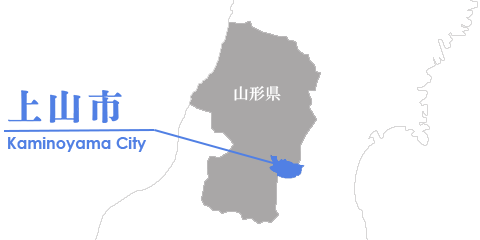市県民税の計算手順
税額の計算方法
「所得割」の課税方法には「総合課税」と「分離課税」があります。通常は「総合課税」ですが、土地・建物・株式等の譲渡所得等には「分離課税」が適用されます。
「総合課税」は、各所得を合計して総合課税分の税額表を適用し計算します。
「分離課税」は、各々の所得区分に応じて分離課税分の税率表を適用し計算します。
「均等割」と「所得割」(総合課税分の税額と分離課税分の税額の合計額)の合計が、市県民税の年税額となります。
市県民税の計算
以下の計算を経て算出されます。
1 前年の収入金額-必要経費等=総所得金額
2 総所得金額-所得控除=課税総所得金額
3 課税総所得金額×税率-税額控除=所得割額(総合課税分のみ)
4 所得割額+均等割額=市県民税額
所得の種類及び内容
所得の種類と算出方法は以下のとおりです。
| 所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 | ||
| 総合所得 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 | |
| 配当所得 | 株式や出資金の配当など | 収入金額-元本取得に要した負債の利子 | ||
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 | ||
| 事業所得 | 営業 | 営業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 | |
| 農業 | 農業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 | ||
| 給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額 または特定支出控除額 |
||
| 雑所得 | 年金、恩給など(公的年金等) | 収入金額-公的年金控除額 | ||
| 他の所得に当てはまらない所得 | 収入金額-必要経費 | |||
| 一時所得 | 生命保険、損害保険契約の満期返戻金など | (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2 | ||
| 譲渡所得 | 短期 | 分離譲渡以外の資産の譲渡 (5年以内の譲渡) |
収入金額-必要経費-特別控除額 | |
| 長期 | 分離譲渡以外の資産の譲渡 (5年超保有の譲渡) |
(収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2 | ||
| 分離課税所得 | 譲渡所得 | 短期 | 土地などの資産の譲渡 (5年以内の譲渡) |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
| 長期 | 土地などの資産の譲渡 (5年超保有の譲渡) |
|||
| 株式等の譲渡所得 | 株式等有価証券の譲渡 | 申告分離課税 | ||
| 上場株式等の配当所得 | 株式や出資金の配当 | 収入金額-元本取得に要した負債の利子 | ||
| 先物取引 | 先物取引に係る雑所得等 | 収入金額-必要経費 | ||
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除)×1/2 | ||
| 山林所得 | 山林の伐採または譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | ||
所得控除の種類と控除額
所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、扶養親族の有無や病気、災害などによる出費があるかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
|
所得控除の種類 |
所得控除が受けられる人と控除額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
納税義務者が勤労学生のとき 控除額:26万円 |
|
所得が48万以下の配偶者がいるとき 控除額:最高33万円 老人対象配偶者は最高38万円 控除額の詳細についてはこちら |
|
|
|
|
|
合計所得金額 2,400万円以下 43万円 |
令和3年度から所得金額調整控除が創設されました。
次の(1)・(2)のいずれか又は両方に該当する場合は、所得金額調整控除が給与所得から控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、イ~ニのいずれかの要件を満たす場合
注:給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円で算出
イ 本人が特別障がい者に該当する
ロ 23歳未満の扶養親族がいる
ハ 特別障がい者である同一生計配偶者がいる
ニ 特別障がい者である扶養親族がいる
◆所得金額調整控除の額=(給与等の収入金額(注)-850万円)×10%
(2)給与所得と公的年金雑所得があり、その合計得が10万円を超える場合
◆所得金額調整控除の額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
▼ 新契約(平成24年1月1日以降契約)
| 支払額 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 全額 |
| 12,000円超32,000円以下 | 支払額の1/2+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | 支払額の1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 28,000円 |
▼ 旧契約(平成23年12月31日以降契約)
| 支払額 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | 支払額の1/2+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | 支払額の1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 35,000円 |
▼ 新契約と旧契約の両方を有している場合
それぞれの控除額の合計額(上限28,000円)となります。ただし旧契約のみで計算した方が有利な場合は旧契約分だけで計算します。
※生命保険料(新、旧)、介護医療保険料(新のみ)、個人年金保険料(新、旧)について、それぞれの控除額を上記の方法で計算し、合計します。
▼ 地震保険料
支払い金額の1/2(上限25,000円)
▼ 旧長期損害保険料
| 支払額 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 全額 |
| 5,000円超15,000円以下 | 支払額の1/2+2,500円 |
| 15,000円超 | 10,000円 |
▼ 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を有している場合
それぞれの合計額(上限25,000円)
※一つの契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択によりいずれか一方の控除の適用となります。
配偶者控除早見表
※納税義務者本人の合計所得金額
| 配偶者の年齢 | 配偶者の所得 | ※900万円以下 | ※900万円 超950万円以下 |
※950万円超 1000万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 48万未満 | 33万 |
22万 |
11万 |
| 70歳以上 | 48万未満 | 38万 |
26万 |
13万 |
配偶者特別控除早見表
※納税義務者本人の合計所得金額
| 配偶者の 合計所得金額 |
※900万円 以下 |
※900万円超 950万円以下 |
※950万円超 1000万円以下 |
|
|---|---|---|---|---|
| 48万円超~100万円以下 | 33万 |
22万 |
11万 | |
| 100万円超~105万円以下 | 31万 | 21万 | 11万 | |
|
105万円超~110万円以下 |
26万 | 18万 | 9万 | |
|
110万円超~115万円以下 |
21万 | 14万 | 7万 | |
|
115万円超~120万円以下 |
16万 | 11万 | 6万 | |
|
120万円超~125万円以下 |
11万 | 8万 | 4万 | |
|
125万円超~130万円以下 |
6万 | 4万 | 2万 | |
|
130万円超~133万円以下 |
3万 | 2万 | 1万 |
税率
| 区分 | 税率 | |
|---|---|---|
| 所得割 (総合課税分) |
市民税 | 6% |
| 県民税 | 4% |
◆ 令和6年度から森林環境税(国税)が始まりました
森林環境税は、年額1,000円が課税され、市県民税の均等割と併せて徴収することとされています。
| 区分 | 令和6年度~ | 平成26年度~令和5年度 | |
|---|---|---|---|
| 均等割 | 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
| 県民税 | 2,000円(※) | 2,500円(※) | |
| 合計 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 森林環境税(国税) | 1,000円 | ー | |
| 合計 | 6,000円 | 6,000円 | |
※やまがた緑環境税1,000円を含みます。
※平成26年度から、東日本大震災からの復興財源確保のため、市民税・県民税の均等割にそれぞれ年額500円が加算されていましたが、令和5年度で終了しました。
(注)分離、株式譲渡、先物取引等の税率は異なります。
税額控除等
税額控除とは、税率を乗じたあとの算出税額から、税額控除の種類に応じて一定金額を差し引くものです。
調整控除
▼ 概要
平成19年に国から地方へ財源が移譲されたことで生じる市県民税と所得税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除です。
▼ 控除される額
1 合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれかの小さい額の5%
(1)人的控除の額の差の合計額
(2)市県民税の合計課税所得金額
2 合計課税所得金額が200万円以上の場合
{人的控除の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
※合計課税所得金額:課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額得割額の合計額
※{ }内の額が50,000円未満の場合は、50,000円として計算します
配当控除
▼ 控除される額
配当控除の対象となる配当所得があり、総合課税を選択した場合は、下表のとおり配当控除が適用されます。
|
区分 |
市民税の 控除率 |
県民税の 控除率 |
||
|
利益の配当等 |
課税所得金額1,000万円以下の部分 |
1.6% |
1.2% |
|
|
課税所得金額1,000万円超の部分 |
0.8% |
0.6% |
||
|
|
課税所得金額1,000万円以下の部分 |
0.8% |
0.6% |
|
課税所得金額1,000万円超の部分 |
0.4% |
0.3% |
||
|
課税所得金額1,000万円以下の部分 |
0.4% |
0.3% |
|
|
課税所得金額1,000万円超の部分 |
0.2% |
0.15% |
||
住宅借入金等特別税額控除
▼ 対象者
所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額があり、平成11年~令和7年までの入居者。
入居初年度は、確定申告が必要となりますので、山形税務署(申告期間中の会場:山形テルサ)で申告してください。
※ 平成19年・20年に入居された方や特定増改築等で住宅ローン控除を受けている方は、対象となりません。
▼ 控除される額
1 特定取得(住宅の取得対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%)に該当しない場合
次のいずれかの小さい金額
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額等の5%の額(上限97,500円)
2 居住開始が平成26年4月から令和3年12月で、住宅の取得対価または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%に該当する場合(注)
(注:令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅で居住開始年月日が令和4年12月末まで)
次のいずれかの小さい額
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額等の7%の額(上限136,500円)
3 居住開始が令和4年1月から令和7年12月の場合
次のいずれかの小さい金額
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額等の5%の額(上限97,500円)
▼ 控除適用のための手続き
平成22年度分以降は、市町村への申告書の提出は原則不要になりました。
勤務先の年末調整(給与支払報告書)や税務署へ提出の確定申告書の内容から、市役所で住民税の控除額を決定し適用します。
※勤務先から提出される給与支払報告書や確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」の記載がない場合には、住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合があります。
寄附金税額控除
▼ 対象寄附金
(1) 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
(2) 日本赤十字社山形県支部、山形県共同募金会
(3) 山形県が条例で指定したもの及び上山市が条例で指定したもの
(対象となる法人・団体は山形県条例、上山市条例とも同じです。詳しくは山形県庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)
▼ 控除される額
以下の(1)基本控除額 (2)特例控除額の合計が控除額となります。
(1) 基本控除額:対象となる寄附金のすべてに適用
(寄付金の合計額-2,000円)×10%
※寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度となります
(2) 特例控除額:ふるさと納税をした場合のみ適用
(都道府県・市区町村に対する寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
※特例控除額は市県民税所得割額の20%が限度となります
▼ 控除適用のための手続き
控除の適用を受けるには、所得税の確定申告または市県民税の申告が必要です。
所得税の確定申告をする方は、市県民税の申告は不要ですが、その場合は確定申告書第二表「住民税に関する事項」への記載が必要です。この記載がもれると市県民税を計算する上で寄附金控除が適用されないことがありますのでご注意ください。
また、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。詳細については総務省(ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ)<外部リンク>にてご確認ください。
配当割額・株式譲渡割額の控除
▼ 控除される額
地方税(配当割や株式譲渡所得割)を差し引かれた配当所得、株式譲渡所得があり、これらの所得を申告した場合には差し引かれた税額を控除します。
市民税:配当割・株式譲渡所得割額の3/5
県民税:配当割・株式譲渡所得割額の2/5
定額減税
令和6年度において、定額減税が実施されます。定額減税についてはこちら